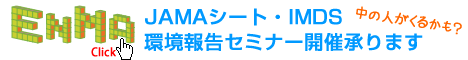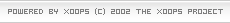Re: JAMPのリスクマネジメント資料
ゲスト
chemSHERPAによるPFASに関する情報伝達で問題なのは…
1.そもそもchemSHERPAに記載されている物質が”PFAS”にあたるのか受け取り側が読み取れない。
2.PFASでCAS番号がないものやCAS番号があってもJAMP管理対象物質に入っていないものをどうchemSHERPA上で表現するのか作成側がわかってない。
辺りかなと考えています。
1.のケースでは、chemSHERPAの成分情報画面に沢山の物質が記載されていても、それがPFASにあたるのかどうか化学的な知識がないとわからない。
個人的にPFASに該当する物質が膨大過ぎてひとつひとつを覚えていられないので、「なんとなく物質名称にフッ素っぽい表現があるなー」という物質はPFASかどうか世の中の資料で検索してみたり、物質検索画面で物質群名にPFASっぽいものが出てくるか確認するんですが、これが結構大変。
chemSHERPA上でPFASにあたるかどうかわかりやすくフラグが立つといいんですけどね。
2.のケースだとchemSHERPAを作る時にCAS番号で検索してみてヒットしなかったら管理対象物質じゃないから載せなくてもいいという運用をしちゃってるところもあるんじゃないかなと・・・。
CAS番号がないんだからchemSHERPAに載せようがないとか。
SN番号を使って記載するルールがあるけど、PFAS以外も含めてこのルールを理解して漏れなく記載できているかどうかは結構怪しいと思ってます。
もちろん”非含有保証にならない”というところもネックですね・・・。
とにかく川下側、川上側、中流域の各社がchemSHERPAについてどれだけ深く丁寧に理解できているかがchemSHERPAを使った外部コミュニケーションのカギなんだと思いますが、今のところは綻びがいっぱいな気がしてます。
1.そもそもchemSHERPAに記載されている物質が”PFAS”にあたるのか受け取り側が読み取れない。
2.PFASでCAS番号がないものやCAS番号があってもJAMP管理対象物質に入っていないものをどうchemSHERPA上で表現するのか作成側がわかってない。
辺りかなと考えています。
1.のケースでは、chemSHERPAの成分情報画面に沢山の物質が記載されていても、それがPFASにあたるのかどうか化学的な知識がないとわからない。
個人的にPFASに該当する物質が膨大過ぎてひとつひとつを覚えていられないので、「なんとなく物質名称にフッ素っぽい表現があるなー」という物質はPFASかどうか世の中の資料で検索してみたり、物質検索画面で物質群名にPFASっぽいものが出てくるか確認するんですが、これが結構大変。
chemSHERPA上でPFASにあたるかどうかわかりやすくフラグが立つといいんですけどね。
2.のケースだとchemSHERPAを作る時にCAS番号で検索してみてヒットしなかったら管理対象物質じゃないから載せなくてもいいという運用をしちゃってるところもあるんじゃないかなと・・・。
CAS番号がないんだからchemSHERPAに載せようがないとか。
SN番号を使って記載するルールがあるけど、PFAS以外も含めてこのルールを理解して漏れなく記載できているかどうかは結構怪しいと思ってます。
もちろん”非含有保証にならない”というところもネックですね・・・。
とにかく川下側、川上側、中流域の各社がchemSHERPAについてどれだけ深く丁寧に理解できているかがchemSHERPAを使った外部コミュニケーションのカギなんだと思いますが、今のところは綻びがいっぱいな気がしてます。
投票数:4
平均点:10.00
返信する
この投稿に返信する
投稿ツリー
-
 JAMPのリスクマネジメント資料
(万事屋稼業, 2025-9-22 15:14)
JAMPのリスクマネジメント資料
(万事屋稼業, 2025-9-22 15:14)
-
 Re: JAMPのリスクマネジメント資料
(TR_wada, 2025-9-22 15:27)
Re: JAMPのリスクマネジメント資料
(TR_wada, 2025-9-22 15:27)
-
 Re: JAMPのリスクマネジメント資料
(ゲスト, 2025-9-22 16:28)
Re: JAMPのリスクマネジメント資料
(ゲスト, 2025-9-22 16:28)
-
 Re: JAMPのリスクマネジメント資料
(TR_wada, 2025-9-22 16:48)
Re: JAMPのリスクマネジメント資料
(TR_wada, 2025-9-22 16:48)
-